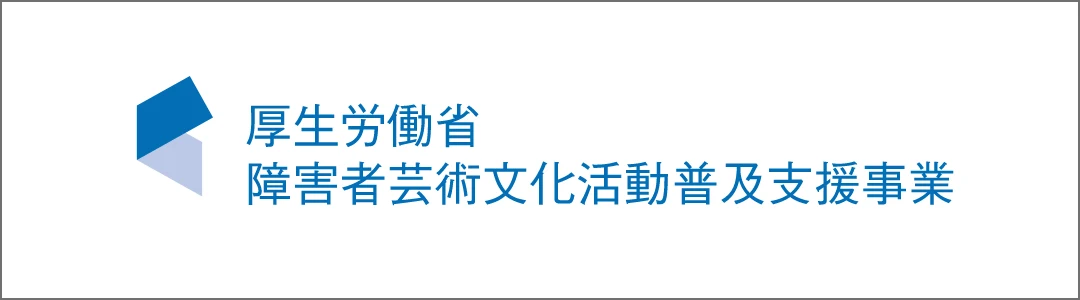
STORIES
ストーリーズ
宮平康生
Miyahira Kouki
破れた画用紙も、作品に。
遊ぶように楽しく、自由に描く
今回訪れたのは「想いをかたちに ともに歩む未来を創る」をミッションに、就労継続支援や生活介護サービス、グループホームを展開する沖縄県うるま市の社会福祉法人 大樹会。お話をうかがったのは、大樹会が運営する就労継続新施設「くわの実」の生活介護プログラムでアート活動を行っている宮平康生(みやひらこうき)さん、そして、施設長の西村夏生(にしむらなつき)さんです。


宮平康生(みやひらこうき)さん(上)と、施設長の西村夏生(にしむらなつき)さん(下)。作品と一緒に撮影させて欲しいという取材陣のリクエストに、宮平さんは照れながらも笑顔で応じてくれました。
宮平康生さん(以下、宮平さん)は、「くわの実」が展開する生活介護サービス内の絵画教室「atelier くわの実」(以下、アトリエ)に参加しています。通常の活動日は週に2日、10時〜14時です。宮平さんは、この2日間に加えて、週に1日、他の利用者が別の活動を行う時間でも作品づくりをしています。
施設長の西村夏生さん(以下、西村さん)によると、宮平さんは、合間に遊びやトイレ、歩き回ったりする時間を取りながら、午前と午後それぞれ1時間くらいを作品づくりにかけているそうです。その中で出来上がる作品数は2〜3枚くらい。

施設内は部屋の壁や廊下、靴箱の上などに作品が飾られています。額に入っている作品(写真左上)と、新聞紙に描かれている作品(写真中央)は宮平さんの作品。
取材当日、最初はアトリエの部屋とトイレや廊下を行ったり来たりしていた宮平さん。その後、気持ちが落ち着いたのか、席につきペンで絵を描き始めました。
「宮平さんと西村さんが並んでいる様子を撮影させてもらえませんか?」という取材陣からのリクエストを受けて、西村さんは宮平さんの横に座ろうとしました。すると、宮平さんは少し恥ずかしそうな表情で、テーブルの上で腕を伸ばして境界をつくるような仕草をしました。その様子を見た西村さんは「嫌だった? ごめーん」とにこやかに話しかける——こんな場面がありました。
宮平さんが、他者と言葉でコミュニケーションをとることはほとんどありません。発したとしても「あー」「うー」など。西村さんは、そんな言葉少ない宮平さんの仕草、表情に寄り添いながら、言葉に変えて気持ちを確認していました。
そんな二人のやりとりからは、とても穏やかな空気が感じられました。

表情豊かな宮平さん。「宮平さんのかわいらしさって、作品にも出てると思うんですよ」と西村さんは話します。
宮平さんは高校を卒業してすぐ、2024年にアトリエでの活動をはじめました。
アトリエに入る前から絵を描いていた宮平さん。絵を描きたくてアトリエに入ったのだと、西村さんは教えてくれました。
以前から宮平さんのお母さんがアトリエのインスタグラムや展示会を見ていたことも、宮平さんのアトリエ参加のきっかけになりました。
知的障害と自閉症スペクトラムのある宮平さんは、道具のセッティングで大事にしている独自のルールがあるようです。
西村さんに教えてもらい気がついたのですが、宮平さんの机の上のペンは、キャップと本体が隣同士に並ぶように置かれています。また、ティッシュの箱は下に丸めたティッシュを挟んでありました。このように、ペンやティッシュの箱の置き方ひとつにも、宮平さんが落ち着くマイルールがありました。

ペンの置き方、ティッシュ箱の置き方にも宮平さんなりのマイルールがあります。
すいすいとペンを走らせる宮平さん。
宮平さんの作品は、てるてる坊主や魚のようなモチーフが描かれているものが多くあります。色はその時、気に入ったものを使っているようです。この日、宮平さんの画用紙には、丸と三角を組み合わせたような形が、ピンクや黄色で描かれていました。


ペンを使ってすいすいと作品を描く宮平さん。てるてる坊主や魚のような形は、宮平さんにとってどんな意味があるのでしょうか。
宮平さんはペンの他に、アクリル絵の具を使って作品をつくる日もあります。
アトリエ内の畳スペースでは、利用者さんの作品が一面に乾かされています。その中には、アクリル絵の具で描かれた宮平さんの作品もありました。
水分たっぷりの絵の具がにじみ、混ざり合って描かれた画用紙は、大小さまざまに破れている……なぜでしょうか。

宮平さんの作品。破れていますが、それぞれのパーツが独立した作品のようにも、合わせて1つの作品のようにも見える不思議さがありました。
画用紙が破れている理由を、西村さんが教えてくれました。
宮平さんが絵の具を使う時は、絵の具に水分をたっぷり含ませて、まず自分の手に塗っていきます。そして、そのまま手で画用紙に描きます。でも、水分が多いため、だんだんと画用紙はしなってきて破れはじめます。すると、宮平さんはそのまま紙を破くんだそう。
そんな宮平さんのユニークな制作スタイルを「感触を楽しんでいるところがあるかもしれない」と、西村さんは説明してくれました。
いわゆる常識的なやり方ではないかもしれませんが、手の平に塗る絵の具の感触、画用紙が破れていく感触は、一体どのようなものなのなのでしょうか。
宮平さんの、具体的な形にとらわれず、色や質感で遊んでいるような作品から感じられる自由さや温かさ、ずっと見ていたくなる心地よさは、楽しく遊ぶような制作スタイルも影響しているのかもしれません。

西村さんによると「 アクリル絵の具の作品で1枚の絵として残っているものは、2〜3枚に1枚くらい」。ということは、こちらは貴重な1枚。見ていて元気のでる明るい色合いは、作成した時の宮平さんの心の色なのかもしれません。
「絵を見て興味を持ち、その作品を描いている人のことを知りたくなる」。そんなふうに、アトリエの利用者と、彼らの作品を見た人がつながっていってほしい——と、西村さんは希望を込めて語ってくれました。
宮平さんにも、以前こんなことがあったそうです。
沖縄県の北谷町で展示会を行った時のこと。
宮平さんのお母さんからの連絡を受けて、なんと、宮平さんの小学校時代の先生がいらっしゃったそう。その時の宮平さんの様子について、西村さんは「とても嬉しそうだった」と話します。

宮平さんの作品が載っているカレンダー(右)とその原画展のポスター(左)。(ポスターの絵は他の利用者の作品)
当時の様子を思い浮かべながら、西村さんは、アトリエの活動と利用者の活動について次のように話してくれました。
「作品の販売や展示会を行うと、アトリエの利用者はそこにおしゃれして行き、来場者から褒めてもらい、おいしいものを食べて帰ってきます。その経験と、嬉しかった体験は利用者の自己主張につながっていくんです」
これからそうした機会が増えていくことで、宮平さんは、より自分自身を表現していくようになることでしょう。これから、宮平さんは、どのような作品を描き、どのような人と出会っていくのか、私たち取材陣も楽しみでなりません。
